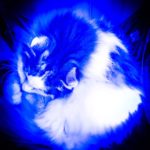文=横堀つばさ
写真=Sleep Lam
2025年3月7日、Blume popoが大阪・Yogibo HOLY MOUNTAINにて自主企画イベント『essais vol.5』を開催した。2019年の始動以降、コンスタントに展開されてきた本企画の第5弾となったこの日は、Blume popoが敬愛するiVyとsidenerdsをゲストに招集。超満員の会場で繰り広げられた3組のライブを振り返る。
* * *
01 / iVy
粛々と降り積もる雪さながらに鳴らされるギターと回転するミラーボール。光を乱反射する12月の街を想起させる世界の下で、トップバッターのiVyは「Hello phila!」を響かせ始めた。エアリーな2人の歌声は冬の外気を連れてきたばかりのフロアの気配と融解しながら、ささやかかつ穏やかに手元へ送られていく。今にも擦り切れてしまいそうなハイトーンのヴォーカルは、藁だって掴みたいほどの縋りつきと心の底では叶わないと直感している無常観を演出する。





トゥインクルなイントロからなだれ込んだ「秋の新曲」では雑踏や波音と思われる環境音がどこからか混入し、点滅するライトと連動しながら踏切で分断された世界や光の届かない深海を出現させる。四分で刻まれるベースとカッティングが導出する同ナンバーのクライマックスは枷を外していく主人公を描きつつも、自由がもたらす不安感をどことなく滲ませており、iVyがチャームとしている朧げなムードと深くリンクしていたのだ。










〈触れてみて 離れてく 離れてく〉〈波立って 続いてって〉と短いワードが細やかなリズムを形成し、ループ・ミュージックと絶妙なマッチを示した「ツキノカケラ」、ポエトリーリーディングとシャウトを連結させることで思わず零れた心情を表現する「かげぼうし」を経て、エンディングを飾ったのは「クラスルーム」。〈理想の城へ 君と2人で 行けたならいいのにな〉と居心地の悪い集団からの逃避を図る1曲が、ここまで引かれていたボーダーラインの内側へ聴き手を誘い、2人きりの独立した世界へ「せーの」で飛び込む光景を描きだした。

* * *
02 / sidenerds
横田檀(Blume popo / Gt.)が愛するsidenerdsは、これまた横田が自らの人生を総括するプレイリストに追加しているというフェイバリット・ソング「わたし」で幕を上げた。〈らしさはいらない? わたしはいつもジェネリックどこかのだれか〉と他者の人生をなぞる日々から発生したアイデンティティの欠落と対峙するこの楽曲は、徐々に熱を加えていくハイハットや揺らぐハーモニクスと連動しながら、何も持ち合わせない自身への焦燥を、渇望を原動力とする野心へ染め直していく。みにあまる雅(Vo. Gt.)が声を張り上げる生々しい手触りのラストやそれに沿って唸るギターは、自己存在をこの場に刻み付けんとするsidenerdsの痕跡だと言えよう。





冒頭でしなやかな身体性を見せつけたからこそ、濃厚な香りを放ったのが「☆。.:*・゜」だった。打ち付けると形容するのがドンピシャなドラミングを中心に、今度は〈曖昧な言葉で誤魔化した〉とロゴスを拠り所にすることの難しさや言語によって簡易化された感情に対する疑問が次々とこぼれていく。肉体も言葉もなかなか信用できないけれど、時に自分と決別して、折に反骨精神を剥き出しにしてあがく姿は美しい。







ピリオドを打った「入水」で矢庭に浮かび上がるみにあまる雅の歌声と、ぽっかりと空いた穴を埋めるように連打されるバンド・サウンドは、そんなsidenerdsの世界に対するわずかに穿った、しかし間違いなく含まれているポジティビティを具現化していたのだ。ガラス花に劣らない繊細な2本のギターの絡み合いと大胆不敵な演奏を点滅させ、ひりつきに膜を張りながら冷たさを加えた4人。分からないままに手探りで転がるsidenerdsの楽曲たちは、自らに問いかけ続けるものであり、それはBlume popoの視線と確実に交わっていた。






* * *
03 / Blume popo
およそ1年ぶりに『essais』へ登壇したBlume popoは「彼方高さから躰放ったあなた」をオープニングに選択。1月にドロップされたEP『Test for Texture of Text』を貫く母音縛りの手法の出発点となった同ナンバーは、どこかハミングしているような鳴りを内包しており、それゆえふいに張り上げられるワードが際立った光を放つ。





最新のBlume popoでオーディエンスを歓迎すると、語りに類する発声とダイナミックなアンサンブルがせめぎ合う「He drowns in the She」や、「楽しい夜にしましょう」と誘った「エントロピー」を通過して、ウ母音にフィーチャーした「渦つむぐ冬」へ。インタビューにて横田檀(Gt.)はウ母音の特徴を「伸ばすことが苦手な分、短音を連続させる手法と相性が良い」と評価した上で、母音が持つイメージに曲調が引っ張られていったという旨を話してくれたが、僅かな余白が頻繁に顔を出すビートはまさしくそうしたウ母音の性質を反映している。

その結果、オーディエンスの頭が小刻みに揺れていたのも興味深いところ。母音のキャラクターを反映した音像は、ファンの鑑賞態度へと作用し、言語という不可視の概念を鑑賞態度として可視化していく。言葉と肉体が相互に作用したこのひとコマは、一見対照的に思える両者が不可分であることを証明すると同時に、彼らがあらゆる角度から自己存在を描こうとしてきた事実を伝えていた。





ライブも終盤に差し掛かり、野村美こ(Vo.)は「このステージにいる時は一番素直で、美しい生き物でいるみたいに思うんです。私たちを世界で一番正しく、美しく、素直でいさせてくれて本当に感謝しています。明日も明後日もこの時間に生かされていると思いますし、この瞬間が明日の血肉になって、主軸になって、主軸の肉付けになって、生きていくんだと思います」とはちきれんばかりの感謝を口にした。そこから、ラストを彩ったのはEP同様「痙攣」と「底」。この2曲をエンディングに添えた意味とは、単にEPの構成をなぞるためではなく、言葉を縛り、通常は使わない頭の筋肉をフル回転させた末に見つけたある種の真理にラインマーカーを引くためだったのではないか。ちっぽけな存在が連合していくことで永遠を生み出す様を描いた「痙攣」も、幼少期の記憶を漁る中で深層に眠っていた歌への、あるいは表現欲求の根幹を掘り起こす「底」も、先刻のMCと交わりながら共存や受容といったテーマを描いていく。意図しない単語選択が白日の下に晒したのは、Blume popoが徹頭徹尾追求してきた他者との関係の中で決定づけられる私の在り方だったのだ。








であるならば、アンコールで披露された「幸福のすべて」は、5人が求めるコミュニティや社会がライブハウスに出現していることの表象だろう。終演の近づきを予感しながらも〈もう、僕らだけ少年のままでいよう〉と誘うこの歌は決してモラトリアムへの招待ではなく、心のトキメキや赴く方向に純粋でいるための切実な願いにほかならない。〈僕らだけの知る言葉を使おう〉。言葉を解体して編み直した先で見つけた私たちだけの合言葉は、思い出を分かち合うことで生まれてくる。野村が自らの血肉になると確信を告げたこの日は、そんな大切にしまっておきたくなる記憶になっていった。








Author